
信託には、いくつかの特有の制度があります。そのうちから後継受益者の指定、残余財産の帰属の指定、信託契約の変更、信託財産の追加の4つの制度についてお話をします。
1.後継受益者の指定
普通の契約は、契約当事者の死亡などにより終了しますが、民事信託は委託者の死後も継続することができ、当初受益者が亡くなった場合も存続させることができます。
信託契約で定める「信託目的」に従って信託財産から金銭の給付などを受ける人を受益者と言い、民事信託では委託者自身を受益者に指定する(自益信託)場合が多いということはこれまでにもお話しています。
委託者(夫)が自分を受益者としていた場合、扶養家族である配偶者(妻)も夫の受益権の恩恵を受けます。
信託目的に、「夫婦が安心して生活を送る」などと書くはずです。
しかし、受益者である夫が亡くなり信託が終了すると、残された妻は、信託から受ける利益を失うことになります。
そればかりではなく、相続手続きが開始されることにより、遺産分割で苦労した挙句、遺産を貰うと今度は相続税の支払いが待っています。これはまさに災難です。
こういう問題を回避するために妻を後継受益者に指定します。
初めから配偶者を受益者に指定しておけばこういう問題は起きませんが、そんな信託が作られるのは、死期が迫った夫が妻のために信託を設定するといった特殊な場合だけです。
夫が先に亡くなった場合に備えて、契約時に妻を次の受託者に指定しておく、これが「後継受益者の指定」です。(法第90条)
後継受益者を指定しておけば、当初受益者である夫が死亡した場合でも信託財産に関する相続が直ちに始まる訳でなく、特段の手続きをしなくても受益者が配偶者に変わるだけで信託が継続するので、妻の生活は安泰です。
夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言を作成しておくという手段はありますが、その場合でも相続になれば遺言の執行手続きが必要ですし、遺留分権利者から遺留分の請求があれば、これに対応しなければなりません。
特に配偶者の判断力が衰え始めていた場合などには、配偶者に負担をかけないためにも後継受益者を指定しておき信託を継続させるのは良い方法です。
ただ、他の相続人にとっては、信託が継続する間に信託財産が目減りする、相続財産が自分のものになる時期が遅くなるという不利益があります。不利益を受ける子供に十分説明して納得が得られないと紛争の原因になりかねません。
私は、ご夫婦から信託の相談を受けたときは、後継受益者を指定する契約を提案していました。
2.配偶者以外の人を後継受益者に指定する
配偶者以外の後継受益者指定は、慎重に考えてください。
不利益を被る相続人が、委託者が亡くなった後で不満を言い出し、家族全員を不幸に陥れる危険があるからです。
母親が後継受益者になることは納得できても、例えば浪費壁のある兄弟の一人に資産が渡るのを遅らせるために兄弟の一人を後継受益者にするような場合は、紛争になりがちです。
良かれと思って考えたことでもあまりお勧めできません。
不肖の子には、遺言で遺留分相当額を相続させ、その余を全て孫に遺贈するなどの民事信託以外の対処方法を考えた方が無難と思います。
3.後継受託者の指定
後継受益者ほど重要ではないのですが、後継受託者についても説明しておきます。受託者がいなくなると民事信託は機能しなくなります。
新しい受託者を据えるか、信託を終了するかのどちらかになりますが、新しい受託者がそう簡単に見つかるとは思えませんし、前任者との事務の引継ぎをどのようにするのかを考えるだけで、目の前が暗くなります。
裁判所に頼んで臨時の受託者を決めてもらい、信託の終了手続きをしてもらうしかありませんが、余計な手間がかかります。
そんな訳で、受託者に事故があった場合に備えて後継受託者を指定しておくことは、見落としがちですが結構重要です。
誰が良いかについては、そう深刻に考える必要はありません。親族であれば誰でも良いのです。
名目だけも受託者になってくれて事務を引き継いだ形を作り、専門家に頼んで信託の終了手続きを進めてもらうのです。
4.残余財産の帰属の指定
信託が終了(法163条)しても、その後始末のため、清算が結了するまでは信託は存続するものとみなされます。
受託者が清算受託者と名前を変えて清算事務を行う(法177条)ことになっています。
未払金や未収金を整理した後、残った資産(残余財産)は、信託行為で定めた人(残余財産受益者)に帰属します(法182条)。
残余財産受益者がいない場合は、委託者又は相続人が帰属者となります。
これが残余財産の帰属に関する法の定めです。
民事信託は新しい法律で、清算に至った事例がまだ少なく、そのため判例なども乏しく、実をいうと、私はこの清算段階での実務の実際を経験していません。
民事信託契約の最後に残余財産の帰属の指定の定めが置かれます。
民事信託は、別名家族信託とも言われているように、委託者の相続人である家族が受託者になるので、受託者を中心とする法定相続人に残余財産を帰属させる場合が大部分です。
この定めは遺言と同じ財産承継の機能を持つ特別な規定です。
民事信託契約公正証書に書かれた残余財産の帰属の定めは、公正証書遺言と同じ強い法的効力がありますから、遺言を作成するのと同様の配慮が必要です。
それだけではなく、簡単には変更できないという大変強い効力を持っており、この強い効力は良いことばかりではないことに注意する必要があります。
5.「遺言」と「残余財産帰属の指定」の効力の違い
遺言は大変強い効力を持つと考えられていますが、それは遺言者が亡くなってからの効力の話で、実は、遺言には「遺言者の存命中はいつでも書き換えが可能」という一見矛盾したような点に大きな特徴があります。
遺言は、遺言者が生きている間は何の効力もなく、亡くなって初めて効力が生じます。
見方を変えると、遺言は、「失敗したと思ったら遺言者は、いつでも一人で書き直しができる」という柔軟な制度なのです。
これに対し、信託の残余財産の帰属の定めは、契約当事者である委託者と受託者の双方の合意がないと変更することができません。
遺言と異なり一人で変更することはできないのです。
残余財産の帰属で財産を貰える人にとっては頼りになる定めですが、委託者からすると、残余財産の帰属で定めたことは失敗したと思っても簡単には変更できない、融通の利かない厄介な制度なのです。
特徴的なのは不動産についての定めです。
不動産の相続について、信託目的の条文に
「不動産〇〇の売却、賃貸、担保設定を禁止する。」
などと特定の不動産の処分を禁止する規定を置けば、受託者は、その不動産を処分することができません。
これに加えて、残余財産の帰属の定めに
「○○の不動産は、甲に帰属させる」
と規定しておくことにより、この不動産を確実に甲に無傷の状態で相続させることができます。
将来の相続を約束された者からすれば頼りになる確実な約束である半面、委託者が失敗したと気が付いても後の祭りです。
遺言は証書にすると確実な約束なように見えますが、実はそうではなく、遺言に記載された不動産でも売却するという最終手段があり、売ってしまえば一瞬で遺言の効力は消滅してしまうという落とし穴があるのです。
ただ、信託目的での不動産の処分の制限は、信託の特徴である不動産を信託財産として運用することにより受益者に利益をもたらすという長所を殺してしまう欠点がありますので、一種の禁じ手です。
注意してください。
民事信託契約書の作成依頼に来られる方の多くは、経済的な安全・安心のある豊かな老後を求めておられますが、信託が終わった後の財産の行方も重要です。
基本的には通常の遺言と同じ感覚で残余財産の帰属の内容を定めるのが良いと思います。
将来の相続紛争が予想される方の場合は、柔軟な対処を可能にする必要もあるはずですから、変更が簡単ではない信託の残余財産の帰属で相続を決めるより(「残余財産の帰属は、遺言での指定に従う。」)、遺言の方が良いかもしれません。
いずれにせよ、経験豊かな弁護士と良く相談してから内容をどうするかを決めることをお勧めします。
なお、信託財産以外に委託者の固有財産がある場合は、この分についての遺言を作成した方が良いでしょう。
また、信託の場合は期間が長いと財産額が大きく変動する可能性があるので、遺留分侵害とならないよう注意する必要があります。
6.信託の変更
民事信託は、当事者による契約ですから、当事者の合意があれば内容を変更することが可能です。
当初の契約を取消し、新たな契約を作成すると考えても良い訳ですが、いずれにしてもその時点で当事者の一人である委託者の判断能力に問題がないことが必要です。
また、民事信託の場合は、委託者の死後にも信託が継続している場合があり、契約内容に受益者に不利益を及ぼしかねない規定がある場合には、これを放置できないという特殊な問題があります。
法149条5項は、委託者が存在しないときの信託の変更に関する規定で
信託の目的に反しないこと
受益者の利益に適合することが明らかなとき
信託監督人の同意
の三つを条件に、信託の変更を認めています。
第三者の立場にある信託監督人を関与させて公平性を担保したことには十分意味があると思われますが、同条第4項に「信託行為に別段の定めがある時は、その定めるところによる。」との規定を置いて条件を変更する定めを当初の信託契約で設定し得おくことを許容しています。
民事信託の柔軟性を尊重すべしとの意図からのものでしょうが、安易に「別段の定め」を置くことには注意を要すると考えています。
特に、家族信託で、将来、信託の定めに変更が必要になる場合とはどのような場合か想像しにくく、家族信託を作成する場合に必須の知識とは思われません。
7.信託財産の追加
当初の金銭信託の額をどの程度の金額とするかは、将来の事情の変化を考えると簡単には決めにくい問題と思われます。
また、当初の信託財産が予想外に早く減少したため、信託財産(金銭)を増やす必要が生じる場合もあるでしょう。
そのような場合に備えて金銭信託の変更規定を設けておくことができますので、
「(信託財産の追加)
委託者は、受託者の同意を得て、金銭を本信託に追加することができる。」
という規定を信託契約に置いています。
この記載で明らかなように、信託金を追加できるのは、委託者だけです。
金銭信託の追加は、例外的な対応かと当初思っていましたが、実際は便利な規定です。
信託金をいくらにするかは委託者の金策の段取りも必要なので重要な作業です。
金銭信託の額を決め、公正証書作成後に、速やかに信託口口座に現金を振り込まないと信託が始まらないのです。
民事信託を手掛けた最初の頃は、委託者の財産保護のためにも可能な限りの金額を信託する方が委託者のためになると思い込んでいました。
しかし、民事信託の委託者は、必ずしも判断能力が衰えたという理由で信託するわけではないのですから、信託開始後も委託者が自由に使える手持ち金を持っていた方が便利であると気が付きました。
ですから信託開始後の状況に応じて、必要であれば追加信託すれば良いと思うようになりました。
委託者以外には追加信託をする人はいませんから、金銭信託の追加により管理する資産が多くなって責任が重くなる受託者の同意があれば良いのです。
手続きとしては、信託口口座に委託者からの入金があればそれで終わりです。会計帳簿上明確な記載がなされればそれで足ります。
なお、不動産の追加信託は、当該不動産に関し利害関係を持つに至った者があり得るところから、慎重に対処する必要があります。
8.まとめ
民事信託は、自由な契約ですから特約を設けることが可能であるだけに、その内容については契約の当事者である委託者の利益を害する可能性はないことを慎重に検討する必要があります。(次回につづく)
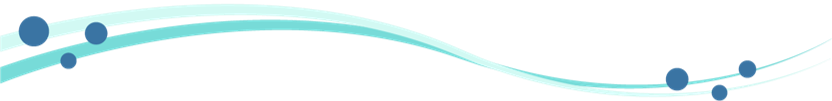
⇓動画でもご紹介しています⇓
【民事信託3-①】民事信託で配偶者を守る!後継受益者・受託者の正しい指定方法とは?_弁護士 加澤正樹 | スペシャリストアライアンス新潟







